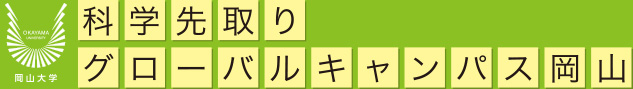薬学系基礎
| 【講座分野】 | 基礎科学 【科目 No.303-1】 |
|---|---|
| 【年月日】 | 2015/11/03(祝・火) 1限目(11:00~12:30) |
| 【講 師】 | 黒田 照夫 |
| 【場 所】 | 岡山大学薬学部1号館 |
| 【授業内容】 |
神経伝達物質“アセチルコリン”を中心物質として、有機化学、微生物学(天然物を含む)、薬理学の観点から解説を行う。 2.微生物学 病原細菌とは? / 毒素とは? |
| 【受講生の感想】 |
◆前回の薬学系基礎の講義の際に、アセチルコリンの模型を作ったので、今回、そのアセチルコリンがどのようなものなのか、また、そのアセチルコリンを抑制したり促進したりする物質についても知ることができて、とても勉強になった。 ◆薬草など自然界に存在する、人に有益なものが、なぜそのような効果を示す薬を作り出すのか、ということを考えるのはとても興味深かった。 ◆将来医師を志しているが、薬を処方し、効果だけでなく、副作用のリスクを認識することの重要性と、毒にも成り得る薬のリスクを考える良い機会になった。 ◆毒の中には、量により薬として利用されているものもあるようなので、どのような薬があるか調べてみたい。 |

|

|
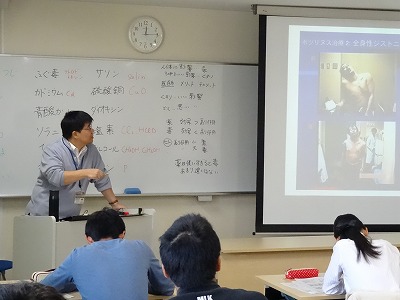
|

|
薬学系基礎
| 【講座分野】 | 基礎科学 【科目 No.303-1】 |
|---|---|
| 【年月日】 | 2015/11/03(祝・火) 2限目(13:30~15:00)・3限目(15:10~16:40) |
| 【講 師】 | 上原 孝 |
| 【場 所】 | 岡山大学薬学部1号館 |
| 【授業内容】 |
神経伝達物質“アセチルコリン”を中心物質として、有機化学、微生物学(天然物を含む)、薬理学の観点から解説を行う。 3-4.薬理学 シナプスとは? / 受容体とは? / アセチルコリンに関係する医薬品がなぜ効くのか? |
| 【受講生の感想】 |
◆メカニズムは同じでも働く場所や強さが違うと薬は全く違う効果になるということを知り、薬学は面白いと思った。 ◆薬は全てに効くのではなく、M1~M5というように、特に効果のある部位があるので複数の薬が作られている、ということが分かった。もっと深く勉強したい。 ◆受容体の構造をコンピュータで模型を作成し、それによって新薬の開発に役立てることができるのは、凄いと思った。 ◆薬学部は病気に効きやすい薬を研究する学部だと思っていたが、人体や生理現象の理解が必要であるということを知り、関心が持てた。以前、副作用を無くすことは可能ではないかと思っていたが、薬は毒であるという認識を持つことができ、今後も生体と薬について学んでみたいと思った。 |
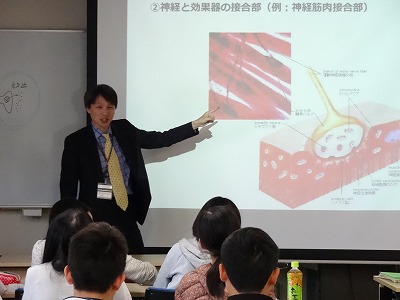
|

|

|

|